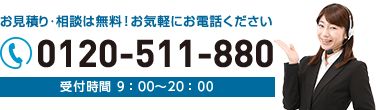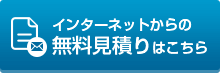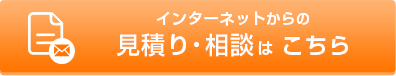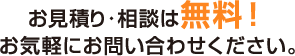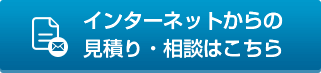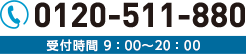お役立ち情報
遺品整理はいつ始める?タイミングの目安と注意点を専門家が解説
2022年10月05日

故人様が旅立たれてすぐの状態では、ご遺族様にとって気持ちも落ち着かず遺品整理どころではないでしょう。それでも、いずれは形見分けや、遺品・遺産の相続を検討しなければならなくなることも……。こちらでは、大阪・奈良の遺品整理を専門に手がけるネクストサポートが、遺品整理や不用品の廃棄に着手する時期やタイミングについて解説します。
遺品整理のタイミングについて
一口に遺品整理に適したタイミングといっても、ご遺族の事情や故人様の生活実態などで大きく変わります。もちろん、目安となる時期はありますが、ケースバイケースで考えるのがベターです。こちらでは、遺品整理や不用品回収に着手するタイミングを決めるうえで、把握しておきたい点を挙げています。
目安となるのは「四十九日」

葬儀から日数が経っていない時期では、ご遺族の心もまだ落ち着いておらず、御香典返しなど事務的な手続きや作業も残っています。そのため、このタイミングは避けるようにしましょう。四十九日を過ぎたあたりであわただしさからも解放され、納骨が済めば気持ちにも一段落がつくので、遺品整理に着手するにはよいでしょう。もちろん、四十九日を待たなくても大丈夫という方はこの限りではありません。
急がないほうがよい場合も

亡くなった方に対する想いは人それぞれ。悲しんでばかりいないで、なるべくすぐに気持ちを切り替え、遺された人々が前を向いて生きていくことが供養になると考える方もいるでしょう。また、中には故人様への愛着が強く、しばらくは気持ちの整理がつかない方もいらして当然です。急いで遺品整理をする必要はありません。特別な事情をのぞいて、気持ちに一区切りがつくまで待つのがよいでしょう。
賃貸の場合は家賃を支払う必要がある

故人様が賃貸アパートや借家に住まわれていたような場合は、部屋をそのままにしておける時間はそう長くありません。一般的には、入居者が亡くなると、できるだけ速やかに退去するよう、管理人や大家から要請されるからです。もし、それでも、なかなか遺品整理に着手できない場合は、その分の家賃を支払う必要がありますが、賃貸の管理者に連絡してできる限り退去日を延期してもらうようにしましょう。
行政・税制的なタイミングに注意

遺品整理をなるべく急いだほうがよい場合もあります。たとえば、故人様の死亡保険の支払い請求や、健康保険証の返却などは速やかに行わなければなりません。しかし、故人様が一人暮らしをされていて室内が散らかっている場合、必要な書類などが見つけにくいことがあります。もちろん、金庫など保管場所がわかっている場合は問題ありませんが、そうでないならできるだけ早い段階で遺品整理を行い、重要な書類、契約書の類を確認しましょう。
また、相続の遺産分割協議書の提出期限は死亡から10ヶ月までと定められているので、相続財産になるような物品がある場合も、可能な限り早めに遺品を整理しておいたほうが無難です。
※手続きをしないまま遺品整理を行うと自動的に相続を単純承認する形となり、後から相続放棄をすることができませんので注意が必要です。
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成はお亡くなりになった日から10ヶ月以内に行いましょう。
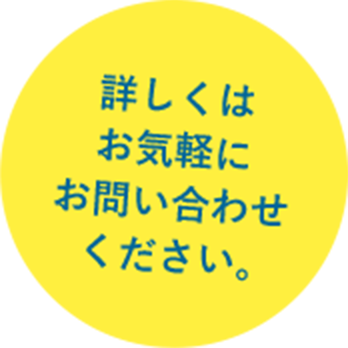
作業料金
1R …15,000円税込〜
 作業料金
作業料金
1R …
15,000円
税込〜
この記事を執筆した専門家

- 株式会社ANJI(アンジ)代表取締役/遺品整理士
-
20歳から引越業界に携わり、現場での豊富な経験を積んだ後、31歳で独立して引越し会社を設立。経営の厳しさと向き合いながらも、実務力と顧客対応力を磨き続ける。その後、廃棄物処理業者での勤務を経て、廃棄物処理・整理の専門知識を習得。36歳で「ネクストサポート」を開業し、遺品整理や生前整理、単身引越しなど、暮らしに密着した支援サービスを開始。
2018年7月に株式会社ANJIを大阪府門真市に設立し、遺品整理・生前整理・家屋の片付けを中心とした事業を展開。現在では年間150件以上、累計2,000件超の整理・片付け実績を誇り、10年以上にわたって築いた現場力と信頼を武器に、地域社会に貢献している。
遺品整理士認定協会より正式に認定を受けた「遺品整理士(認定番号:IS06624)」として、倫理と誠実を重んじる作業を心がけており、依頼者の心に寄り添う姿勢には定評がある。現場での知識と経験を活かした情報発信にも力を入れている。
最新の投稿
 遺品整理・片付け2023年12月15日【感謝の手紙】遺品整理で見つかる愛のメッセージとその向き合い方
遺品整理・片付け2023年12月15日【感謝の手紙】遺品整理で見つかる愛のメッセージとその向き合い方 遺品整理・片付け2022年10月5日【ケース別】遺品整理の進め方と注意点|状況に応じた対処法を解説
遺品整理・片付け2022年10月5日【ケース別】遺品整理の進め方と注意点|状況に応じた対処法を解説 遺品整理・片付け2022年10月5日遺品整理はいつ始める?タイミングの目安と注意点を専門家が解説
遺品整理・片付け2022年10月5日遺品整理はいつ始める?タイミングの目安と注意点を専門家が解説 遺品整理・片付け2022年10月5日失敗しない遺品整理業者の選び方|安心して任せられる4つのチェックポイント
遺品整理・片付け2022年10月5日失敗しない遺品整理業者の選び方|安心して任せられる4つのチェックポイント